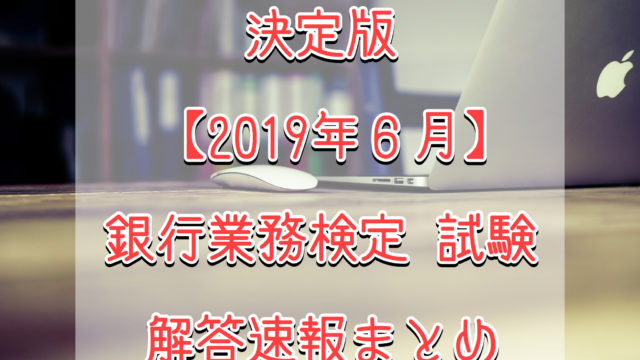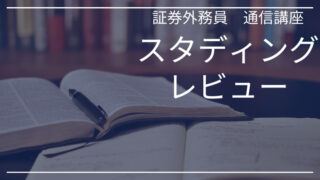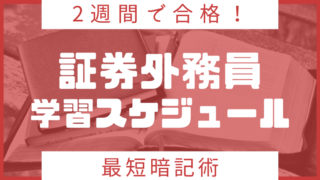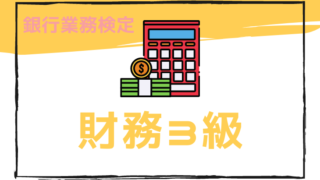営業店マネジメントってどんな問題が出題されるの?
難易度を教えて!
銀行業務検定 営業店マネジメントⅡを受験する方へ
銀行業務検定 23系統 36種目 全種目を分析してきたわたしが、そんなあなたの疑問にお答えします。
営業店マネジメントⅡの合格攻略ポイント

試験概要
| 対象 | 初級管理者またはこれから管理職を目指す中堅行職員 |
| 内容 | 金融業務に関する実務知識のほか、マネジメント全般の知識およびそれにもとづいた応用力について |
| 試験時間 | 180分 |
| 出題形式 | 四答択一式 40問 (各1点) 記述式 6題(各10点) |
| 科目構成 | ・マネジメントの基本 ・人と組織のマネジメント ・業務のマネジメント ・営業推進 ・一般常識 |
| 合格基準 | 60%以上 |
| 試験実施 | 年2回(6月・10月) |
| 関連科目 | ・金融リスクマネジメント2級 ・営業店マネジメントⅠ |
合格率と難易度
営業店マネジメントⅡの過去の受験者数と合格率は以下の通りです。
受験者数 | 合格率 | |
|---|---|---|
| 2023/6 (第155回) | 1,063名 | 43.56% |
| 2022/10 (第153回) | 1,172名 | 49.06% |
| 2022/6 (第152回) | 1,178名 | 40.66 % |
| 2021/10 (第150回) | 1,470名 | 55.24% |
| 2021/6 (第149回) | 1,522名 | 54.73% |
| 平均合格率 | 50.65% |
小規模な試験で、難易度は初級〜中級レベルです。
受験者の平均年齢は38歳と高く、初級管理職の受験者が多いことが予想されます。
受験者の年齢も高く実務経験があることが、高い合格率の要因かも
口コミ
受験者もすくないため、あまり口コミを見つけることができませんでした。
情報が少ないと不安になりますが、過去の出題傾向をしっかり把握して、万全の体制で試験に臨みましょう!
受験者の少ない、マイナー試験
過去問分析
どんな問題が出題されるの?
過去の出題問題のうち、正解率が30%以下と特に低かった問題をまとめました。
試験日 | |
|---|---|
| 2023/6 (第155回) | 管理手段の7要件 労務管理(育児・介護休業法) 顧客情報の管理(個人情報保護法) リスクマネジメント(災害対策) 所得倍増プラン カーボンニュートラル |
| 2022/10 (第153回) | 人を動かす3原則 地域課題・中小企業支援等 チームビルディング 高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン |
| 2022/6 (第152回) | デジタルトランスフォーメーション パーパス経営 コンサルティング営業の推進 市場調査と自店のポジショニング |
営業店マネジメントⅡは2019年より「営業店管理Ⅱ」をリニューアルしています。
出題範囲を一部変更し、マネジメントで初級管理者が抱える課題についての試験となりました。
以前と変わらないレベルでつくられています。
記述式問題もあり、出題範囲が広いですが、過去の問題集で出題傾向を把握すれば、確実に合格できる試験です。
過去問の演習で対策は十分!
さまざまな出題パターンに備えて実務にも生かせる学習を!
営業店マネジメントⅡのおすすめテキスト
最短合格を目指すなら、問題解説集のみに集中して取り組むべし
営業店マネジメントⅡには公式テキストはありません。
実務に即した学習をしたい方は、関連図書を参考にしましょう。
試験直前になると書店では品薄になったり、ネットでは超高値で転売されてしまうので早めの購入をおすすめします。
またメーカー取り寄せになると時間がかかるので注意してください。
できればテキストは最新版を買ってください。
なぜなら私自身、古いテキストを使って直近の出題傾向の変更に対応できずに不合格になってしまったことがあるからです。
テキスト代+受験料代を無駄にしないためにも、最新版で勉強することをおすすめします。
最新テキストで、一発合格!
営業店マネジメントⅡの勉強方法と勉強時間

試験まで時間がないひとへ、合格するための効率的な勉強法のポイントを解説します!
勉強方法
- 問題解説集を3周以上
- 類題のみを解いて定番テーマの理解を深める
- まちがった問題はノートにまとめる
くわしくは、銀行業務検定のための効率のいい勉強法【注意点とコツを解説】を参照!
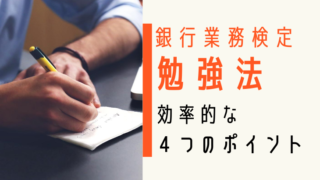
働き方改革など、制度が新しくなった分野は、学習開始前に確認しよう!
勉強時間
営業店マネジメントⅡ
勉強時間の目安は2週間
勉強時間に関しては、個人の予備知識・実務経験などがどれだけあるかに大きく左右されます。
申し込みと同時に、テキストを購入し一読しておくことをおすすめします。自分の実力と試験のレベル感を知ることができるので勉強の計画を立てやすくなると思います。
のこりの時間を有効的につかうなら「元銀行員が教える!超効率的な銀行業務検定の勉強計画の立て方」を参考に、ギリギリじゃない合格を目指して!

営業店マネジメントⅡの解答速報
試験後すぐに解答を確認したい場合は、こちらのサイトがおすすめです。
こちらのサイトは、受験者の投票によって解答が多数決でわかる仕組みとなっています。
試験終了後は、サーバーが繋がりにくくなりますが、すこし時間をおいて確認することをおすすめします。
確実な正答ではありませんが、合格ラインの目安に活用してください。
約2万人が利用しています!
参考程度に活用してください!
銀行業務検定試験の合否通知は、試験後1ヶ月以降に郵送にて通知されます。
また、3日後の17:00〜経済法令研究会にて正答発表がおこなわれます。
確実な正答は、3日後!
営業店マネジメントⅡの次に受けるべき試験は?
上位試験である営業店マネジメントⅠは、営業店長をはじめとする営業店経営についての試験です。
参考書「営業店マネジメントの実務」は営業店マネジメントⅠでも活用できます。

営業店マネジメントⅡを受験される中堅行員の方々であれば金融コンプライアンス・オフィサー2級や経営支援アドバイザー2級などのよりマネジメント力を高めたり実務での知識を深掘りするような試験をおすすめします。
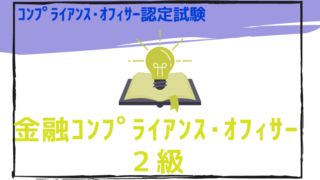
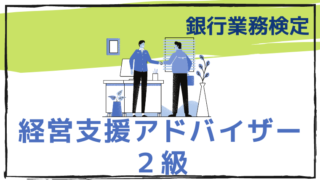
いまは、新設された試験で「外貨建保険販売資格試験」を受験する方が多いです。
2022年までに必須の資格です。
まだ取ってないひとは早めに取得を!
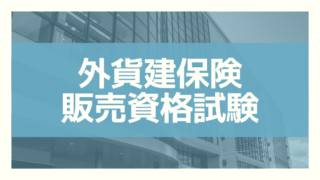
まとめ
- 初級管理者向けの、択一・記述式の試験
- 難易度は初級〜中級レベル
- 過去問を中心に、2週間で合格が狙える
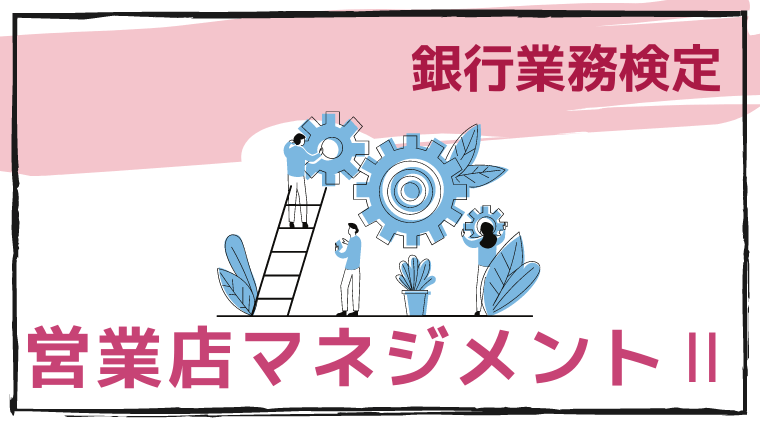



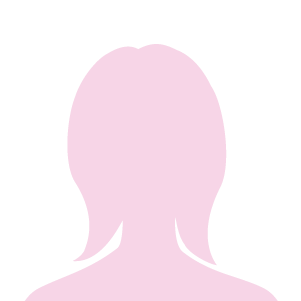



![CBT金融AMLオフィサー[実践]のアイキャッチ画像](https://kijineko55.com/wp-content/uploads/2021/04/cbt-kinyuamlofficerjissen-640x360.png)